日常会話での聞こえについて
会話で大事な周波数(ヘルツ)は500から2000ヘルツの範囲です(下図)。
この範囲の聴力が30デシベル(赤線)より上にあれば会話に支障ありません。
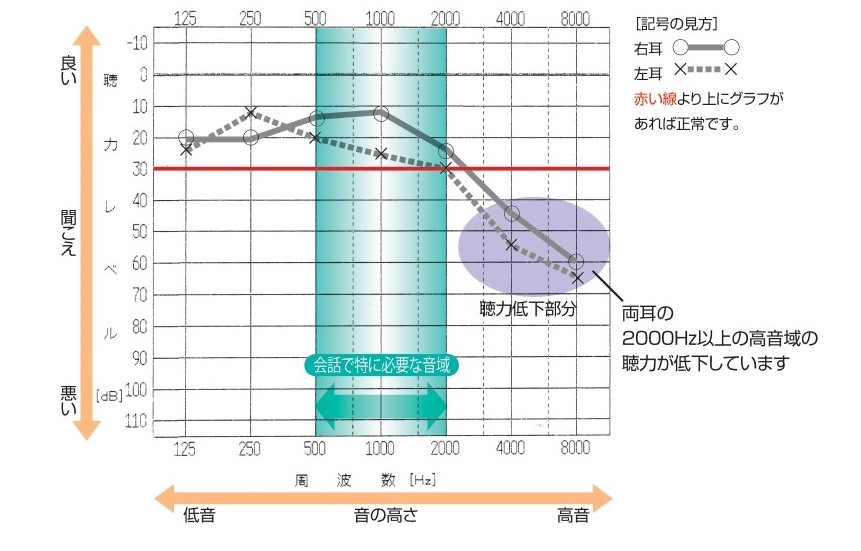
加齢性難聴の初期症状
みなさんこのような症状はみられないですか?これらは加齢性難聴の初期症状です。その際は難聴の早期発見、治療が大切ですので、お早めに耳鼻咽喉科専門医や補聴器相談医を受診しましょう。
◎テレビの音が大きくなった
◎話す声が大きくなった
◎耳鳴り
◎お風呂がわいた電子音が聞こえない
◎体温計の音が聞こえない
加齢性難聴の特徴
加齢性難聴の原因は、耳の中にある音を察知する有毛細胞が、加齢により少なくなることで起こります。有毛細胞は再生しないため、一度、難聴になると治らないのが特徴です。年齢とともに高い音が聞きづらくなる傾向があります。早い人では50代からその症状が出る人もいます。聴力の低下とともに、耳鳴りを自覚することも多くなります。これらは病気ではなく、加齢に伴う現象ですので、難聴や耳鳴りの改善は困難な場合が多いのが現状です。今後、加齢に伴い聴力低下が進行する場合もあります。難聴が生じると会話がスムーズに出来なくなるため、他人との接触を避けるようになります。そうなると、家へのひきこもりにつながり、外部からの刺激が低下するため、うつ病や認知症の発症につながることもあります。会話に不自由を感じるようでしたら、補聴器の検討をされるのもよいかと思います。その際は医師にご相談ください。
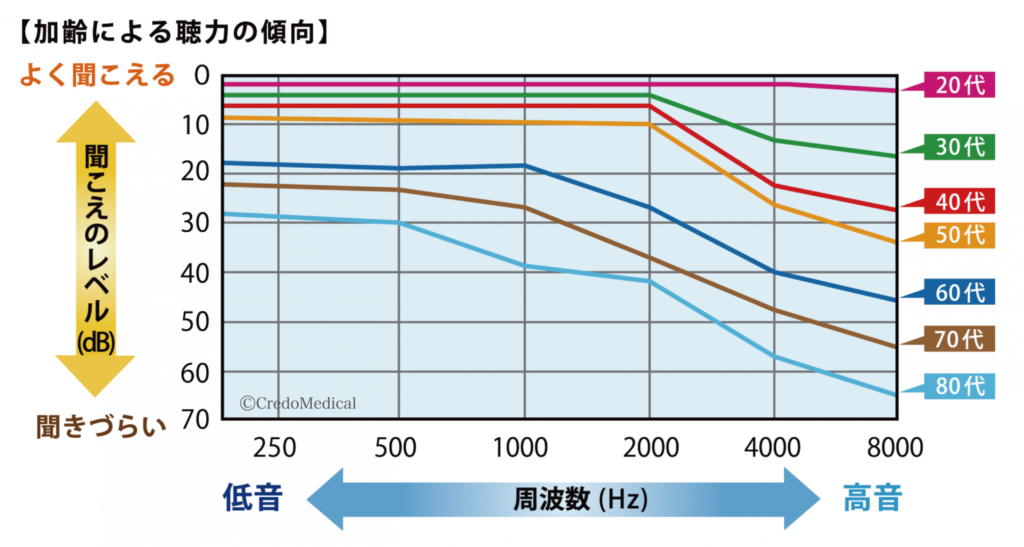
加齢性難聴を進行させないために
◎必要以上に大きな音でテレビやラジオ、音楽を聴かない
大きな音に慣れすぎると、小さな音が聞こえなくなります。
◎塩分や脂質を控えめな食事にする
高血圧や高コレステロール血症、糖尿病などの生活習慣病は内耳の血流を悪くさせ、難聴の進行につながります。
◎禁煙
喫煙することで血管が収縮し血流を悪くします。
◎有酸素運動
適度な有酸素運動は血流の促進につながります。1日30分のウォーキングやジョギングなどを日課にしてみましょう。
◎イヤホンではなくヘッドホンを使用する
イヤホンよりヘッドホンの方が耳への負担が軽くなります。
執筆・監修医師紹介
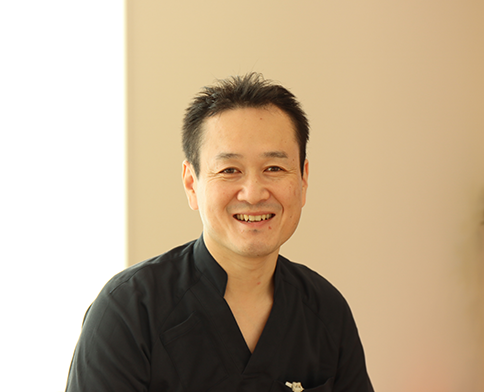 院長/医学博士
院長/医学博士
楓みみはなのどクリニック 院長 中下 陽介
経歴
-
- 関西医科大学 医学部医学科 卒業
- 広島大学大学院 医歯薬学総合研究科 卒業
- 広島大学関連病院勤務
- 木沢記念病院 耳鼻咽喉科 副部長
- 岐阜大学医学部付属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教(臨床講師)
- 中濃厚生病院 頭頸部・耳鼻咽喉科 部長
- 楓みみはなのどクリニック 院長
認定・資格
-
- 日本専門医機構認定耳鼻咽喉科専門医
- 日本耳鼻咽喉科学会認定補聴器相談医
- 日本耳鼻咽喉科学会認定騒音性難聴担当医
- 日本めまい平衡医学会認定めまい相談医
- 日本医師会認定健康スポーツ医
- 博士(医学)広島大学
- 補聴器適合判定医師

